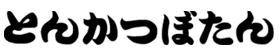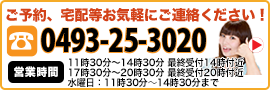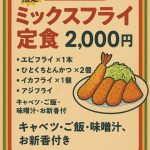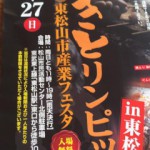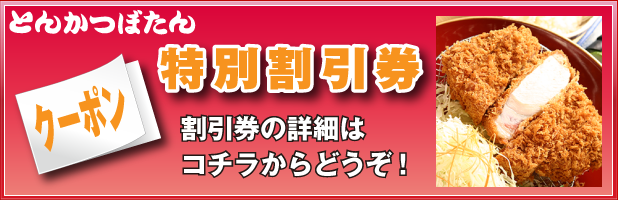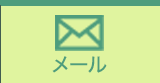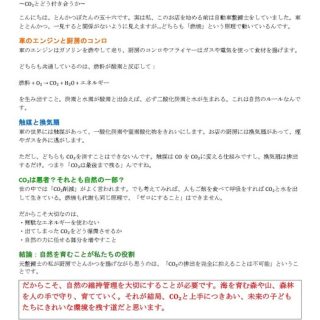
元整備士が語る「燃焼」と「とんかつ」
〜CO₂とどう付き合うか〜
車のエンジンと厨房のコンロ
車のエンジンはガソリンを燃やして走り、厨房のコンロやフライヤーはガスや電気を使って食材を揚げます。
どちらも共通しているのは、燃料が酸素と反応して:
燃料 + O₂ → CO₂ + H₂O + エネルギー
を生み出すこと。炭素と水素が酸素と出会えば、必ず二酸化炭素と水が生まれる。これは自然のルールなんです。
触媒と換気扇
車の世界には触媒があって、一酸化炭素や窒素酸化物をきれいにします。お店の厨房には換気扇があって、煙やガスを外に逃がします。
ただし、どちらもCO₂を消すことはできないんです。触媒はCOをCO₂に変える仕組みですし、換気扇は排出するだけ。つまり「CO₂は最後まで残る」んですね。
CO₂は悪者?それとも自然の一部?
世の中では「CO₂削減」がよく言われます。でも考えてみれば、人もご飯を食べて呼吸をすれば CO₂と水を出して生きている。燃焼も代謝も同じ原理で、「ゼロにすること」はできません。
だからこそ大切なのは、
・無駄なエネルギーを使わない
・出てしまったCO₂をどう循環させるか
・自然の力に任せる部分を増やすこと
元整備士の私が厨房でとんかつを揚げながら思うのは、「CO₂の排出を完全に抑えることは不可能」ということです。
だからこそ、自然の維持管理を大切にすることが必要です。海を育む森や山、森林を人の手で守り、育てていく。それが結局、CO₂と上手につきあい、未来の子どもたちにきれいな環境を残す道だと思います。
今日も厨房の炎と油の音を聞きながら、「とんかつを揚げることも、自然を守ることにつながっている」と感じています